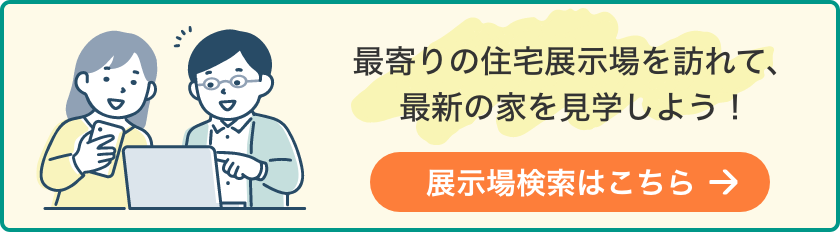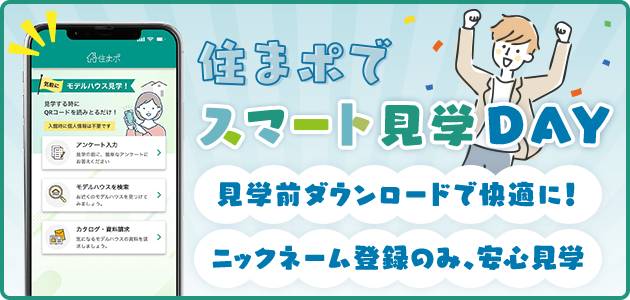家づくりは楽しい反面、土地や建物、融資など、決めなければならないことが多く、大変だと感じる方も少なくありません。実際に「家づくりはブラックボックスなのでは?」と思うほど複雑で、住宅会社や不動産会社に勧められるままスケジュールに追われ、「よくわからないまま、なんとなく納得して進めてしまった」という方もいるようです。
「本当はこうしたかったけれど、仕方がない」「これしか選択肢がなかったから」と、どこかで我慢することが当たり前だと思っている方も多いのではないでしょうか。
株式会社oricon MEが実施した「2025年 満足度の高いハウスメーカー 注文住宅ランキング」によると、1位のメーカーの満足度は81.0%、28位のメーカーでも69.0%という結果でした。この数値を見て、皆さんはどう感じますか?注文住宅は自分で多くのことを決められるはずなのに、意外と満足度が高くないように見えます。
この満足度には、「住宅性能」や「デザイン」「設備・内装の質」といったハード面だけでなく、「営業担当者の対応」や「施工担当者の対応」といった人的な対応面など、13項目にわたる幅広い評価が含まれています。そのため、高得点を獲得するのが難しいのかもしれません。
これこそが、家づくりの難しさです。住宅そのものに不満はなくても、関わる人や進め方への不満が生じると、全体の満足度は下がってしまいます。せっかくの家づくりを楽しむためには、どんなポイントを意識し、どのようにすれば本当に満足できる家づくりができるのかを、改めて考えてみる必要がありそうです。
目次 <Contents>
家づくりが「わかりにくい」と感じる10の理由
家づくりは、初めての方にとって“わかりにくい”ことが多いものです。特に費用・スケジュール・仕様などの複雑さは、専門知識がないと理解が難しく、ストレスを感じる原因になります。ここでは、家づくりで多くの方が「わかりにくい」と感じるポイントを10項目にまとめました。
| わかりにくいポイント | 内容 | 改善策 |
|---|---|---|
| 総予算の全体像がつかめない | 仕様変更による追加費用が多く、総額が予定を超えてしまう。 | 変更追加費用を考え「全体総額」を住宅会社と施主が共有。家具・家電費用も考慮。 |
| 見積書の内容が専門用語だらけ | 各社で表現が異なり、素人には理解しづらい。 | 各項目の説明や費用配分を確認し、比較表を作成する。 |
| 仕様・設備のグレードが不透明 | 「標準仕様」と言われても内容が不明確。 | 実物や図面で仕様を確認し、比較リストを作成。 |
| 希望の間取りにならない | 法的・構造的な制約で要望が通らない。 | 設計段階で制約理由を明確にし、代替案を検討する。 |
| 契約までの流れが複雑 | 仮契約や着工承認などステップが多い。 | スケジュールを可視化し、進行を共有する。 |
| 土地と建物の担当が別 | 情報共有不足で建築制約が後から判明する。 | 担当者間の情報共有体制を確認し、早めに土地条件を把握。 |
| 住宅ローンの選び方が難しい | 種類が多く判断が難しい。 | 専門家やファイナンシャルプランナーに相談。 |
| 工事中の進捗が見えにくい | 現場見学しても理解しにくい。 | 定期的な進捗報告を依頼し、写真付きで確認。 |
| 引き渡し後の保証が不明確 | 「10年保証」と言われても範囲が曖昧。 | 保証内容と対応窓口を契約前に確認する。 |
| 住宅会社とのコミュニケーション | 担当者によって対応や連携に差があり、要望が社内で共有されず行き違いが起こる。 | 担当者間で情報共有できる仕組みのある会社を選ぶ。 |
なぜ家づくりは「ブラックボックス化」するのか
家づくりは「高額」「専門的」「長期間」という3つの要素が重なり、一般の消費者では理解しきれないほどの情報量と意思決定が求められます。高額な契約だからこそ、追加費用が小さく感じられたり、専門的な部分は「任せておけば大丈夫」と思い込んでしまったり、長期にわたる工程の中で「自分は次に何をすればいいのか」が分からなくなることもあります。
こうした状況の中で生まれるのが、
- 情報の非対称性(業者だけが理解している状態)
- 担当者依存の説明(会社ではなく個人の力量によって理解度が変わる)
- 随時情報提供・即決依頼(判断を迫られやすい)
という3つの構造です。これらが重なることで、施主は「よくわからないまま家づくりが進んでいる感覚」を持ちやすくなります。
【後悔しない家づくり】住まポと専門コンサルで賢く進める準備術
家づくりの計画がまだ具体的でなくても、まずはいろいろなモデルハウスを見学し、家づくりのイメージづくりから始めましょう。見学を通じて自分の好みやライフスタイルに合うデザイン・間取りを確認し、知識を蓄えていくことが大切です。
見学の際には、モデルハウス見学アプリ「住まポ」に対応した展示場を利用すると便利です。ニックネームだけで見学できるため、個人情報を伝える必要がなく、営業される心配もありません。気軽に多くのモデルハウスを比較できるのが魅力です。
また、家づくりを第三者的な立場からサポートしてくれるコンサルティングサービスの利用も検討してみましょう。複数の住宅会社の見積もり比較や、補助金対応、スケジュール管理、施工内容のチェックなどを代行してくれるサービスであれば、費用以上の価値が期待できます。

家づくりはまだ具体的でなくてもOK!モデルハウス見学から始める理想の住まい探し
現在では、家づくりといっても新築だけでなく、中古住宅を購入してリフォームやリノベーションを行う人も全体の約3割を占めています。とはいえ、具体的な住まいのプランが決まっていないと、「モデルハウスを見学しても意味がないのでは」と感じてしまう方も多いでしょう。
しかし、家づくりは時間をかけてじっくり準備することが大切です。スケジュールに追われて十分に検討できないまま進めてしまうと、結果的に「もう少し考えればよかった」と後悔してしまうことにもなりかねません。そうならないためにも、まだ具体的な計画がなくても、積極的にモデルハウスを見学し、知識や情報を蓄えることが大切です。
そんな時に便利なのが、新しいスタイルの見学体験ができるアプリ「住まポ」です。見学したいモデルハウスに設置されているQRコードを読み取るだけで、住所や氏名を入力せずに見学が可能。気に入った住宅会社があれば、アプリから簡単に資料請求や問い合わせができます。営業を受ける心配もなく、自由に多くのモデルハウスを見て比較できるのが魅力です。
住まいづくりのプランがまだ固まっていない段階でも、自分の暮らし方を考えるきっかけとして、住宅展示場を積極的に活用してみましょう。多くのモデルハウスを体感し、営業担当者の話を聞くことで、自分の好みや理想の住まい像が少しずつ見えてきます。
そのうえで、土地の条件や予算、ライフプランを踏まえて、「新築がいいのか」「中古住宅を購入してリフォーム・リノベーションをするのか」「今の住まいを活かすのか」など、自分にとって最適な暮らし方をじっくり考えていきましょう。
出典:株式会社oricon ME「2025年 満足度の高いハウスメーカー 注文住宅ランキング」