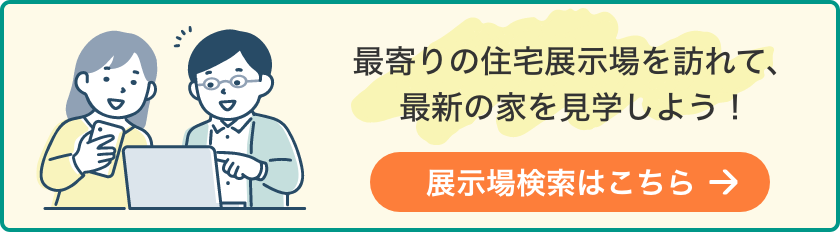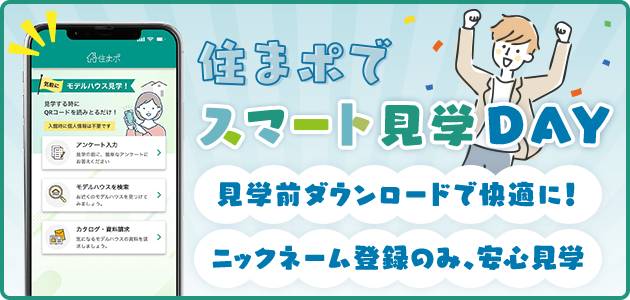この間までは「過去最高の猛暑日数」などと話題になり、暑い暑いと言っていましたが、最近は肌寒さを感じる季節になってきました。夏と冬の気温差が極端になっている現代では、普段暮らしているマイホームの温度管理がとても大切です。外がどれだけ暑くても寒くても、自宅に入るとホッとできて、心地よい温度で、しかも省エネなら最高ですよね。その鍵となるのが「断熱性能」です。
断熱性能が高い住宅は、温度調整に使うエネルギーが少なくて済み、経済的なメリットも大きくなります。住宅の断熱性能基準は年々更新され、新しい素材や工法、設備も次々と登場しています。中古住宅を購入する際にも、どの年の断熱基準をクリアしているかによって快適性が大きく変わってくるため、重要なチェックポイントになります。
目次 <Contents>
中古住宅は1999年が分岐点!断熱基準が大きく変わった理由
以下の基準変更の一覧を見ると、大きな転換点は1999年です。1992年の旧基準から、断熱性能に求められる数値が大幅に引き上げられました。その結果、断熱材の厚さは1992年基準では50〜75mmで良かったものが、1999年基準では100〜120mmが最低基準となり、窓も単層ガラスから複層ガラスが標準仕様になりました。つまり、中古住宅を探す場合、1998年築と1999年築では断熱性能の基準値が大きく異なるということです。
もちろん、中古住宅購入後にリフォームを前提とするなら築年にこだわる必要はありませんが、当時の基準値がそもそも違うということを知っておくことは大きなメリットになります。
| 年代 | 基準・制度 | 概要・特徴 | 断熱基準目安※ |
|---|---|---|---|
| 1953年以前 | 寒冷地住宅促進法など寒冷地での断熱化開始点 | 寒冷地を中心に断熱化の必要性に着手。全国的には断熱仕様の統一基準なし。 | 多くが無断熱または低断熱 |
| 1979年 | 住宅金融公庫仕様書に「断熱工事」が工事項目として初めて明記。 | 住宅ローン融資仕様に断熱が明記され、断熱材の使用が少しずつ普及。義務化ではない。 | ― |
| 1980年 | 「旧省エネルギー基準」制定(初の住宅用省エネ基準) | 住宅の外皮性能(断熱・気密)に関して初めて数値基準が設定された。断熱等性能等級では「等級2」に相当とされる。 | UA ≦ 約1.67(Q値:約4.8) |
| 1992年 | 「新省エネルギー基準」改正 | 断熱性能などを再度強化。断熱等性能等級「等級3」相当。 | UA ≦ 約1.54(Q値:約4.5) |
| 1999年 | 「次世代省エネルギー基準」改正 | 断熱・気密・設備性能を大きく向上。断熱等性能等級「等級4(当時)」相当。 | UA ≦ 約0.87(Q値:約2.7) |
| 2013年 | 「2013年省エネルギー基準」改正 | 14年ぶり大改正。外皮性能だけでなく一次エネルギー消費量も評価対象に。断熱等級では等級4が基準として明確化。 | UA ≦ 約0.87(Q値:約2.7) |
| 2016年 | 「2016年省エネルギー基準」改正 | 建築物省エネ法関連で住宅の評価・表示制度、説明義務など制度面が強化。断熱性能自体の基準数値は25年基準から大きな変更なし。 | UA ≦ 約0.87(Q値:約2.7) |
| 2022年 | 断熱等性能等級5・6・7が新設 | 高性能住宅(特にZEH・超高断熱)を対象に、さらに上位の断熱等級が整備された。 | 等級5:UA ≦ 約0.60/等級6:UA ≦ 約0.46/等級7:UA ≦ 約0.26 |
| 2025年 | 住宅新築時の省エネ基準適合義務化(等級4相当以上) | 今までは義務化されていなかった新築住宅の省エネ基準適合が義務付けられる予定。将来的には等級5以上が標準化へ。 | UA ≦ 約0.87(等級4相当) |
要注意!断熱性能が低い家が招くトラブルとリスク
断熱性能が低い住宅には、暮らしや健康、そして家計にさまざまなデメリットがあります。ここでは主な3つのリスクを紹介します。
光熱費が余分にかかる
断熱性能が低い家は快適な温度を保つために多くのエネルギーが必要となり、その分光熱費が高くなります。
ChatGPTの試算では、低断熱の住宅は年間約30万円、標準断熱で約18万円、高断熱では約9万円と、大きな差が出る結果となりました。

ヒートショックのリスク
家の中の温度差が大きいと、入浴時などに急激な温度変化が起こり、心筋梗塞や失神、転倒事故を引き起こす「ヒートショック」のリスクが高まります。特に寒い季節は要注意です。
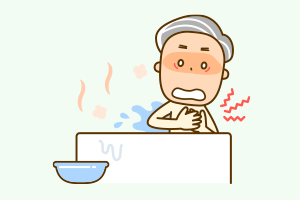
結露による健康被害
断熱が不十分な家では、壁内や窓に結露が発生しやすく、そこからカビやダニが繁殖してしまいます。これが原因で、ぜんそくやアレルギーといった健康被害につながることもあります。

断熱性能は目に見えない部分だからこそ、軽視してしまいがちです。しかし、快適性・健康・光熱費に大きな影響を与える重要な要素です。断熱材の種類や工法、施工の質によって性能は大きく変わるため、住宅選びや家づくりではしっかりと確認し、モデルハウスで実際に体感して比べることが大切です。
断熱工法の種類と特徴を解説!快適な家づくりに必要な基礎知識
住宅の断熱工法や素材にはさまざまな種類があります。まずは、住宅会社が採用している主な断熱工法や素材の特徴をまとめてみました。住宅会社やモデルによって採用する工法は異なり、多様な断熱方法が存在します。
| 断熱工法 | 特徴 | 使う素材 |
|---|---|---|
| 内断熱 | 柱の間に断熱材を詰めて断熱する標準的な断熱工法。リフォームでも施工しやすく、コストも安いが施工精度が低いと隙間ができて性能を維持できない事がある。 | グラスウール、ロックウール、発泡プラスチックなど |
| 外断熱 | 構造柱の外側を断熱材で覆うため、構造材による分離の影響を受けず、高い気密性を保持できる。 | XPS、EPS、硬質ウレタン、フィノールフォームなど |
| 内外断熱 | 内断熱と外断熱の併用。高い断熱性能を得やすいがコストが高くなり、壁厚が増える事となる。 | 内断熱素材+外断熱素材 |
| 吹付断熱 | 建築現場にてウレタンフォームを直接吹き付けて施工する。隙間なく施工できる反面、施工者の技量に左右されたり、経年収縮の可能性もある。 | 吹付ウレタンフォーム |
さらに、基礎断熱工法や床下断熱工法などを組み合わせることで、各社はより高い断熱性能を実現する工夫を行っています。断熱性能は快適性や省エネ性能に直結するため、モデルハウスなどで実際に体感して確認してほしい重要なポイントです。
断熱性能が高ければ、エアコン1台で家全体を快適に空調管理できたり、家の中の温度差が少なく、ヒートショックのリスクを軽減した暮らしが可能になります。
寒さを感じない家へ。断熱と換気方式の違いを分かりやすく解説
断熱性能と合わせて考えなければならないのが「換気性能」です。断熱性能を高めるには、魔法瓶のように外気をしっかり遮断することが理想ですが、その一方で室内の二酸化炭素や汚染物質を排出しにくくなるという問題が生じます。室内の汚染物質には、ダニの死骸やホコリといったハウスダストのほか、建材に含まれる化学物質、化粧品や殺虫剤など日用品の成分まで多岐にわたります。
快適な室温を保ちながら、これらの汚染物質をきちんと排出し、空気環境を整えることが重要です。こうした背景から、2003年の建築基準法改正では住宅の換気が義務化されました。
換気方式にはいくつかの種類があり、住宅では主に「第1種換気」と「第3種換気」が採用されています。この2つの大きな違いは、特に冬の「寒さを感じにくいかどうか」という点です。断熱性能が高くても、換気方式の選び方によっては室内で寒さを感じてしまうことがあります。しかし、寒さの感じ方は個人差が大きいため、実際に体験して確かめることが大切です。
| 換気方式 | 特徴 | メリット・デメリット |
|---|---|---|
| 第一種換気 | 給気・排気ともに機械制御で行う。 | 熱交換器を使い、寒さを感じにくく、空調ロスが少ない。設備・工事費が高い。 |
| 第二種換気 | 給気のみ機械制御で行う。 | 主に病院やクリーンルームなどで採用される。やや肌寒く感じる。住宅には不向き。 |
| 第三種換気 | 排気のみ機械制御で行う。 | 低費用でできるため一般住宅に多いが、直接外気が入るので寒さを感じやすい。 |
家づくりで大切なのは、実際に「体感すること」です。カタログやインターネットでは分からないことも、モデルハウスを見学することでしっかり実感できます。特に断熱性能は目に見えず、感じ方にも個人差があるため、複数のモデルハウスを体験しながら比較することが重要です。
先ほど触れたように、断熱や換気の方法にはさまざまな種類があります。それぞれの特徴や費用を把握し、モデルハウスで実際に体感することで、その違いを理解しやすくなります。

住まい探しは展示場から!「住まポ」で楽しく家づくり準備
今では家づくりは新築だけでなく、中古住宅を購入してリフォーム・リノベーションする人も3割ほどいます。とはいえ、具体的な住まいのプランが決まっていないと、モデルハウスの見学はハードルが高いと感じる方も多いでしょう。しかし、家づくりはじっくり準備することがとても大切です。準備不足のまま進めてしまうと、スケジュールに追われて十分に比較検討できず、流されて決めてしまうことになりがちだからです。
そうならないためにも、まだ家づくりが具体的でなくても、積極的にモデルハウスを見学し、知識を蓄えたり比較したりすることが重要です。そこで役立つのが、気軽にモデルハウスを見学できる新しい仕組み「住まポ」です。住所・氏名の記入は不要で、見学先のQRコードを読み込むだけで来場登録が完了。気軽に見学でき、気に入った住宅会社があれば資料請求や問い合わせもアプリから簡単に行うことができます。
住まいのプランが固まっていなくても、住まポを使って住宅展示場を有効活用し、自分の暮らし方を探すところから始めてみましょう。多くのモデルハウスを体感し、比較し、営業担当者の話を聞くことで、家づくりに必要な知識や視点が自然と身についていきます。
そのうえで、土地の条件や予算、ライフプランを踏まえて、新築が良いのか、中古住宅を購入してリフォーム・リノベーションするのか、あるいは住み替えが適しているのか、自分にとっての最適な選択肢をじっくり考えていきましょう。
出典
- 学ぼう!ホームズ君「H28年基準 省エネ基準の変遷」
- 株式会社エムズアソシエイツ「断熱性能等級はこう変わる!義務化によるこれからの地域別基準と性能アップの秘訣を解説」
- 株式会社アサンテ「中古住宅や古い家屋の断熱性能はどれくらい?断熱等級の変遷もご紹介」
- 断熱材.jp「省エネ基準の変遷と基準値について詳しく解説!」
- 旭化成建材「断熱のすすめ」